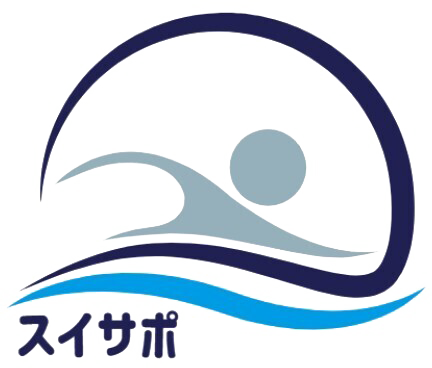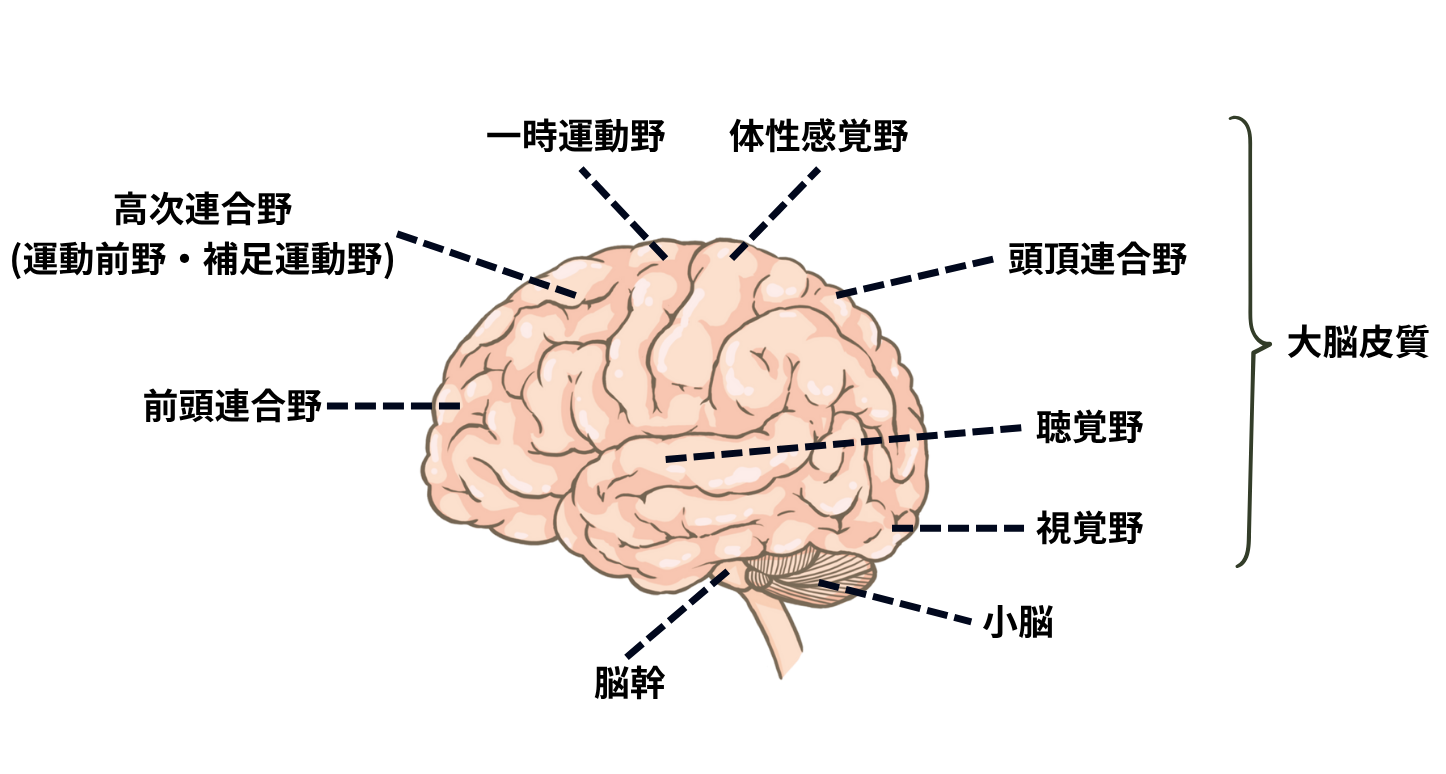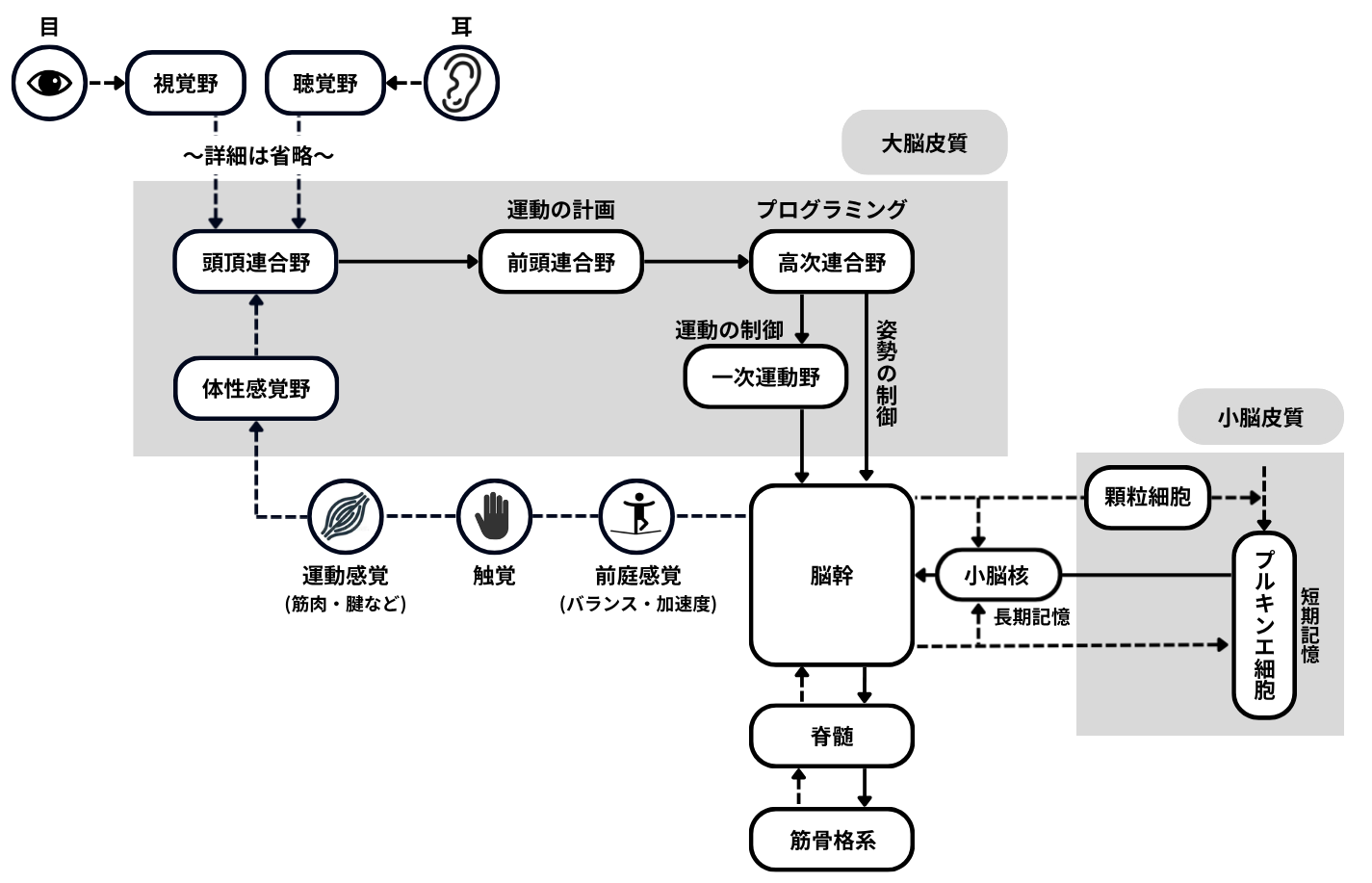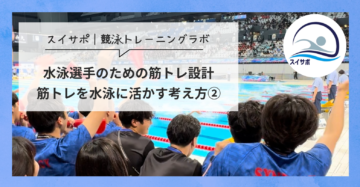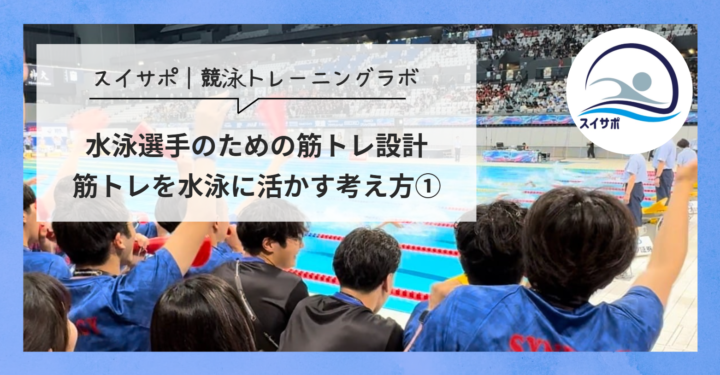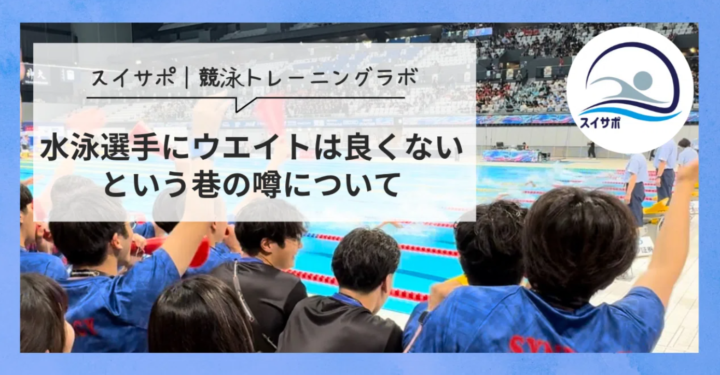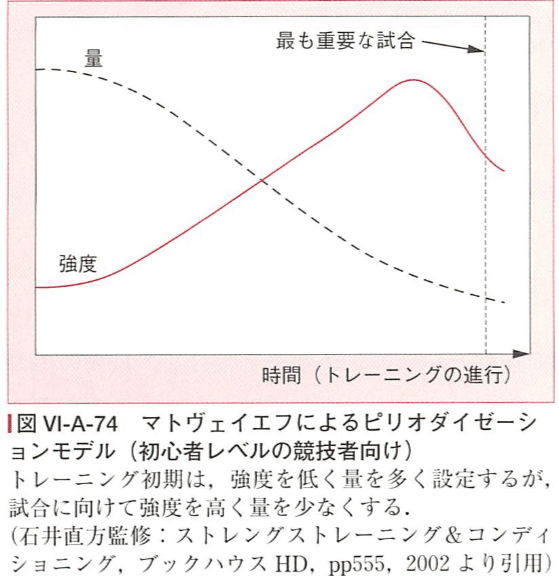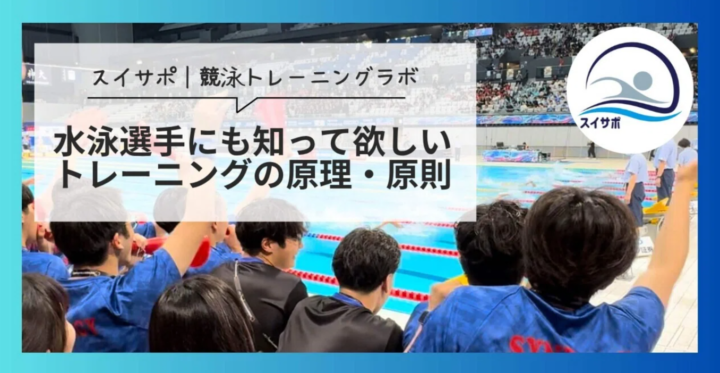突然ですが、練習中にこんなフィードバックを受けた事はありませんか??
「肩甲骨から動かして」「体幹を絞めて」
「キャッチの角度はこうして」
「〇〇を意識して」というタイプのアドバイス。
「考えすぎだよ、もっと自然に!」
「レース中はそんなこと考えないでしょ?」
「意識してはいけない」というアドバイス。
真逆のアドバイスですが、どちらも一度は聞いた事があると思います。
どちらを参考にすれば良いのでしょうか?
今回は、このテーマの解決の糸口を探すために、運動制御理論 前編をご紹介していきます。
内容も難しく、少し長いですがお付き合いください。
あなたは歩く時に何を考えてますか?
突然ですが、歩く時にどの様に身体をコントロールしていますか??
恐らく、何も考えていないと思います。
しかし、歩行動作は意外と複雑なんです。
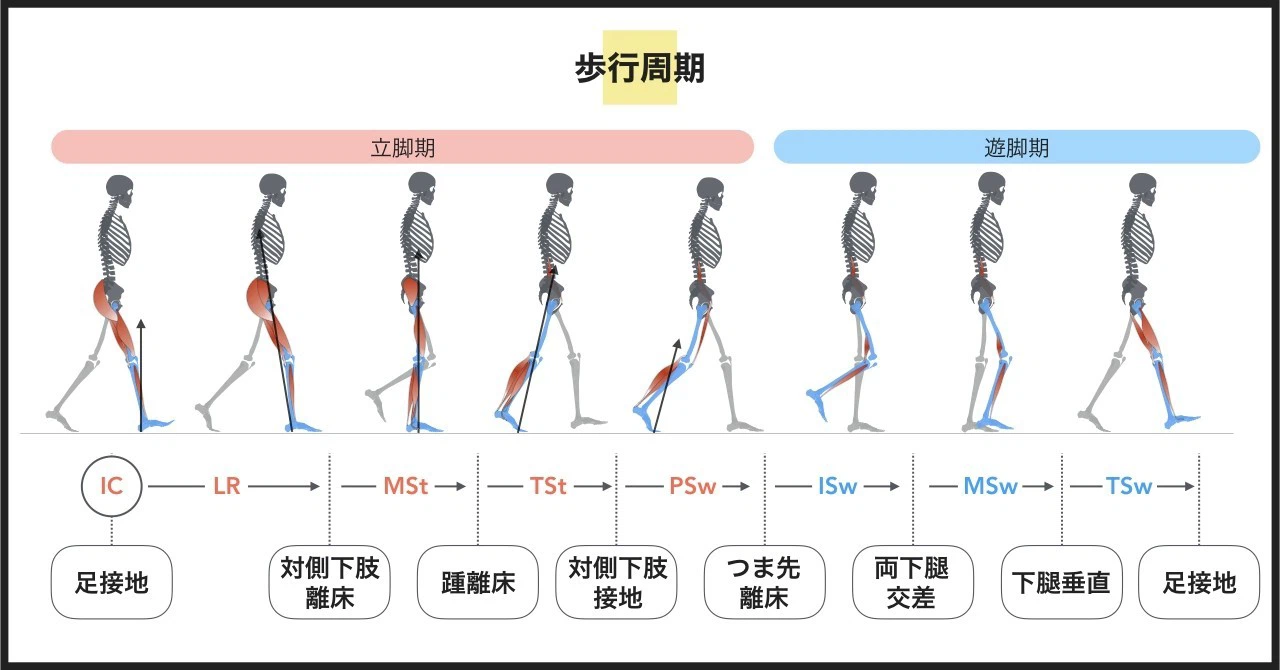
🦶右足の踵が付く(IC)/右足が地面に触れる瞬間
主に使う筋肉:大殿筋(おしり)、中殿筋(おしり横)、大腿二頭筋(もも裏)
🦶右足を踏み込む時(LR〜MSt)/体重をしっかり右足に乗せる瞬間
主に使う筋肉:大殿筋、中殿筋、大腿四頭筋(もも前)、前脛骨筋(すね前)
🦶右足で蹴る時(TSt〜PWw)/右足のつま先で地面を押し出す瞬間
主に使う筋肉:腓腹筋・ヒラメ筋(ふくらはぎ)、腸腰筋(股関節前)
🦶右足を前に蹴り出す時(ISw〜TSw)
主に使う筋肉:腸腰筋(股関節前)、大腿直筋(もも前)、前脛骨筋(すね前)
さらに、足の裏の重心移動は、画像の様に行います。

さて、これらを意識しながら歩いてみてください。
どうでしょう?
普段慣れている動きなのに、考えた途端まともに歩けないですよね??
これは、水泳でも同じことが言えます。
と言う事は、何も考えない方が良いのでしょうか?
結論 (持論)
「体幹を締める」「肩甲骨を動かす」「全身を連動させる」など、
陸上で補える要素は陸上で済ませてしまう。
そして、水中では「キャッチ」「タイミング」など、
水中でしか習得できない項目に集中できるようにする。
この切り分けが重要だと考えています。
この前提のもとで整理すると、、、
▶︎ スイム練習(Aerobic・Dive・試合) は「基本考えない」
▶︎ドライやウエイトの第一・第二段階は「考える」
▶︎ドライやウエイトの第三段階や水中のドリル練習、フォーム修正などのメニューは「初期は考える→反復して徐々に考えない様にして行く」
これが良いのではないかと考えています。
つまり、「意識するか・しないか」どちらが正しいかではなく、
「どう使い分けるか」が大切だと思うのです。
その理由を「運動制御理論」の視点から解説していきたいと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
トレーニングの段階分けについて
👉慶應水泳部の選手はこちら
👉一般の方はこちら
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
水泳選手がより効率よくトレーニングをするための理論運動制御理論とは?
当然ながら、人間が身体を動かす際には脳が指令を出しています。
運動制御理論とは、「身体の動きを目標とする姿勢や動作に向かって、効率的かつ適応的に調整・制御する脳と神経系の仕組み」と言えます。
一体どのように身体を動かしているのでしょうか?
少し難しい話ですが、確認してみましょう。
水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論人間の脳 と 運動制御の回路について
人間の脳 と 運動制御の回路について、こちらは覚える必要はありませんが、「こんな感じなのね」と捉えておいて下さい。
この内容を基に解説していきます。
水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御①【知覚】
運動の制御は、
まず「自分の身体の状態がどうなっているのか?」
これを知る段階から始まります。
(今回は、目や耳については割愛します。)
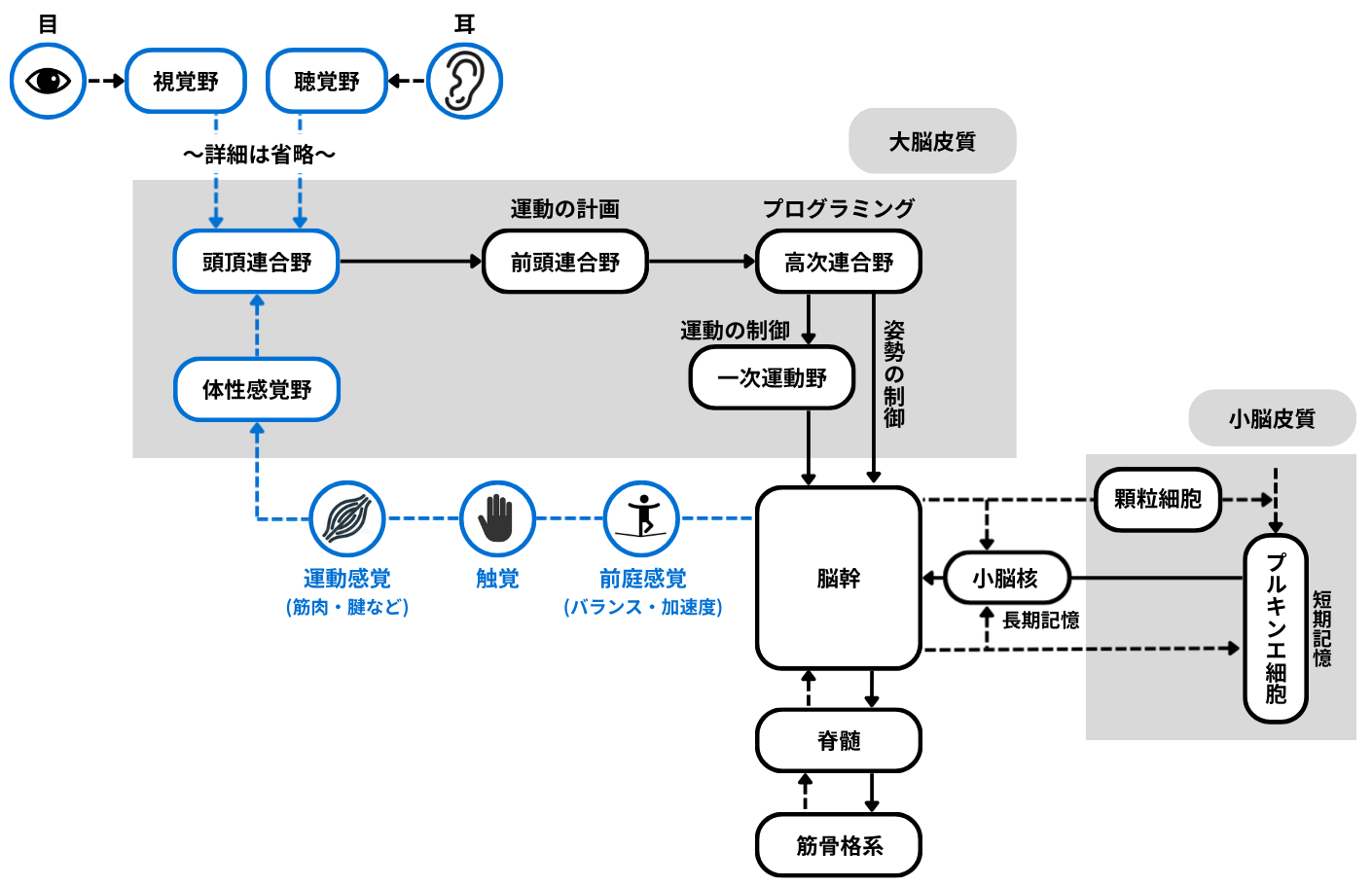
図1:知覚
①目:目で見た情報
②耳:耳で聞いた音
③前庭感覚:バランス感覚や加速度 (移動速度など)
④触覚:皮膚に触れた感覚
⑤運動感覚:筋肉や腱などの組織
③~⑤を合わせて体性感覚と言い、これらから得た情報を基に自分の身体の状態を把握し、運動の計画を立てていきます。
水泳で言うならば、以下の通りです。
▶前庭感覚:浮力・泳速・重心移動・ターン(方向転換)
▶触覚:水圧・水温・水深・水感
▶運動感覚:筋肉の張り・筋肉の収縮
水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御②【運動計画】
さて、体性感覚から得た情報を基に運動を計画していきます。
図2の青い部分ですね。
いわゆる、コードを書いている状態ですね。
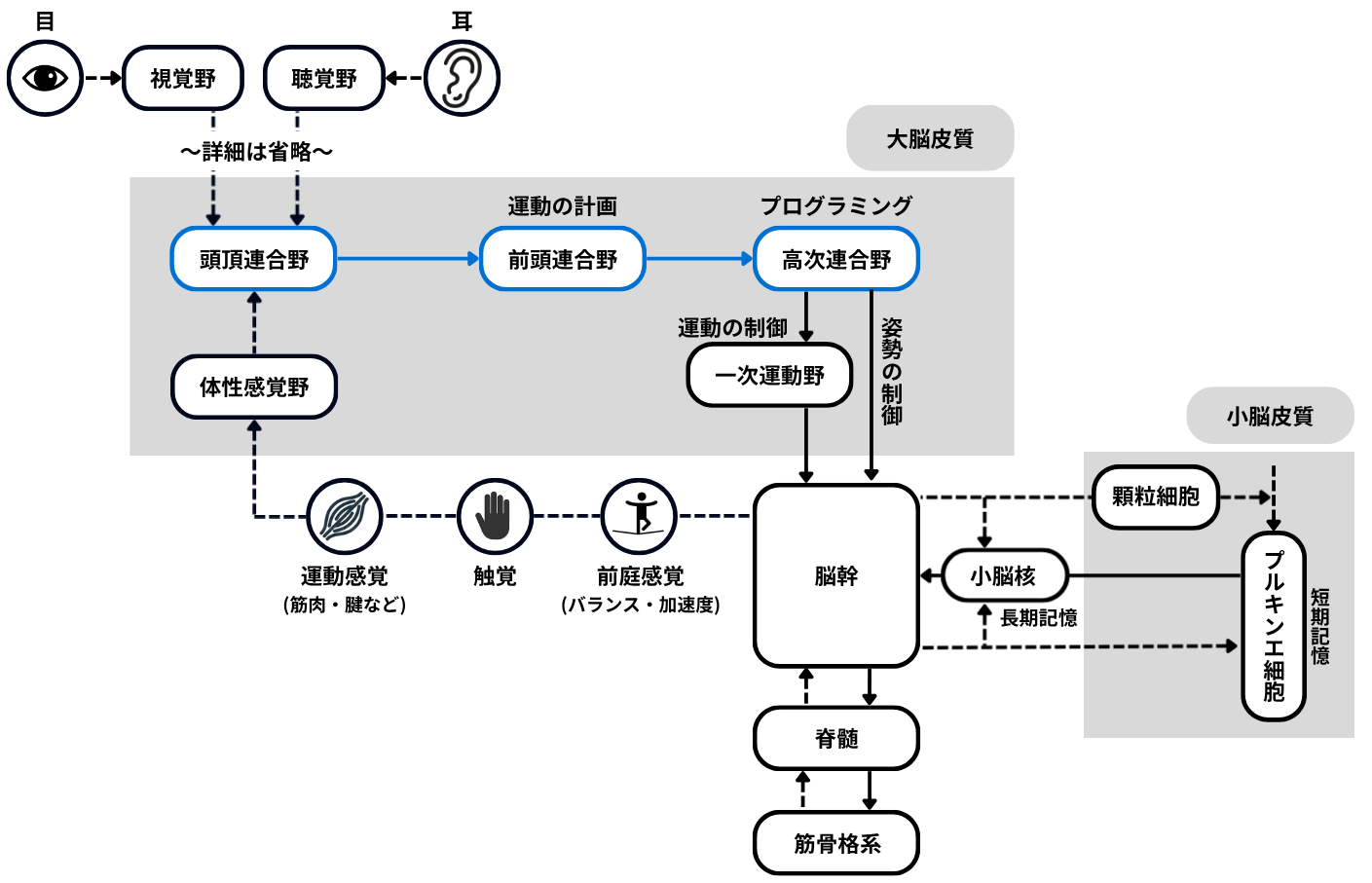
図2:運動計画
水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御③【運動指令】
運動のプログラミングが終わると、動作が開始します。
この時、運動の指示は2通りに分かれます。
①姿勢を維持する指示
②四肢の動きなど、姿勢以外の指示
この2つのうち、姿勢の維持が優先されていきます。
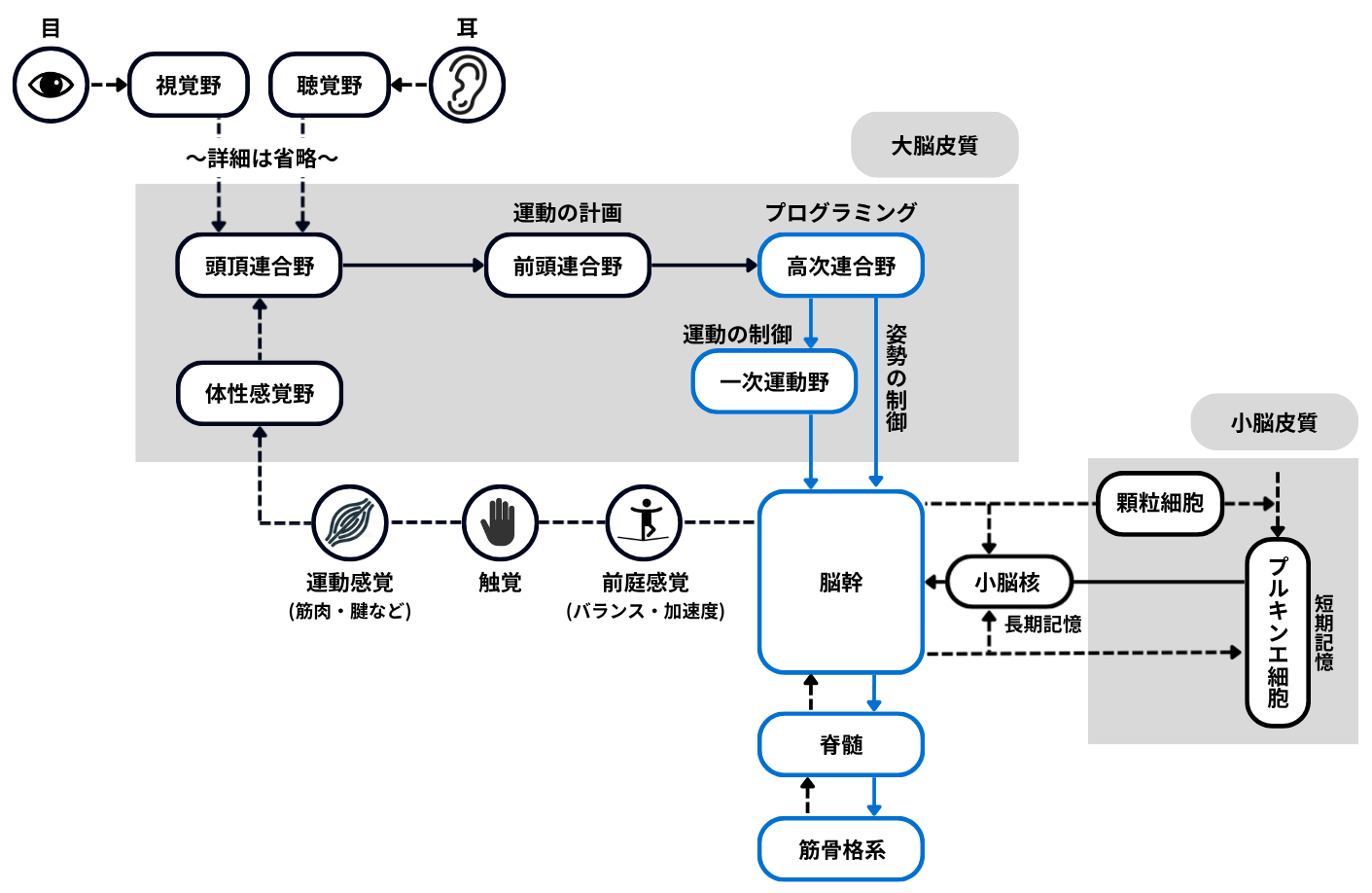
図3:運動指令
姿勢の維持については、
高次連合野→脳幹→脊髄→筋骨格系へと
比較的処理が早いのですが、
四肢などの動きは、
高次連合野→一次連合野→脳幹→脊髄→筋骨格系
と少しラグが生じます。(0.1秒程だそうです。)
水泳選手がより効率よくトレーニングをするための運動制御理論運動制御④【フィードバック制御】
さて、筋骨格系へと指示が届くといよいよ動作が起こります。
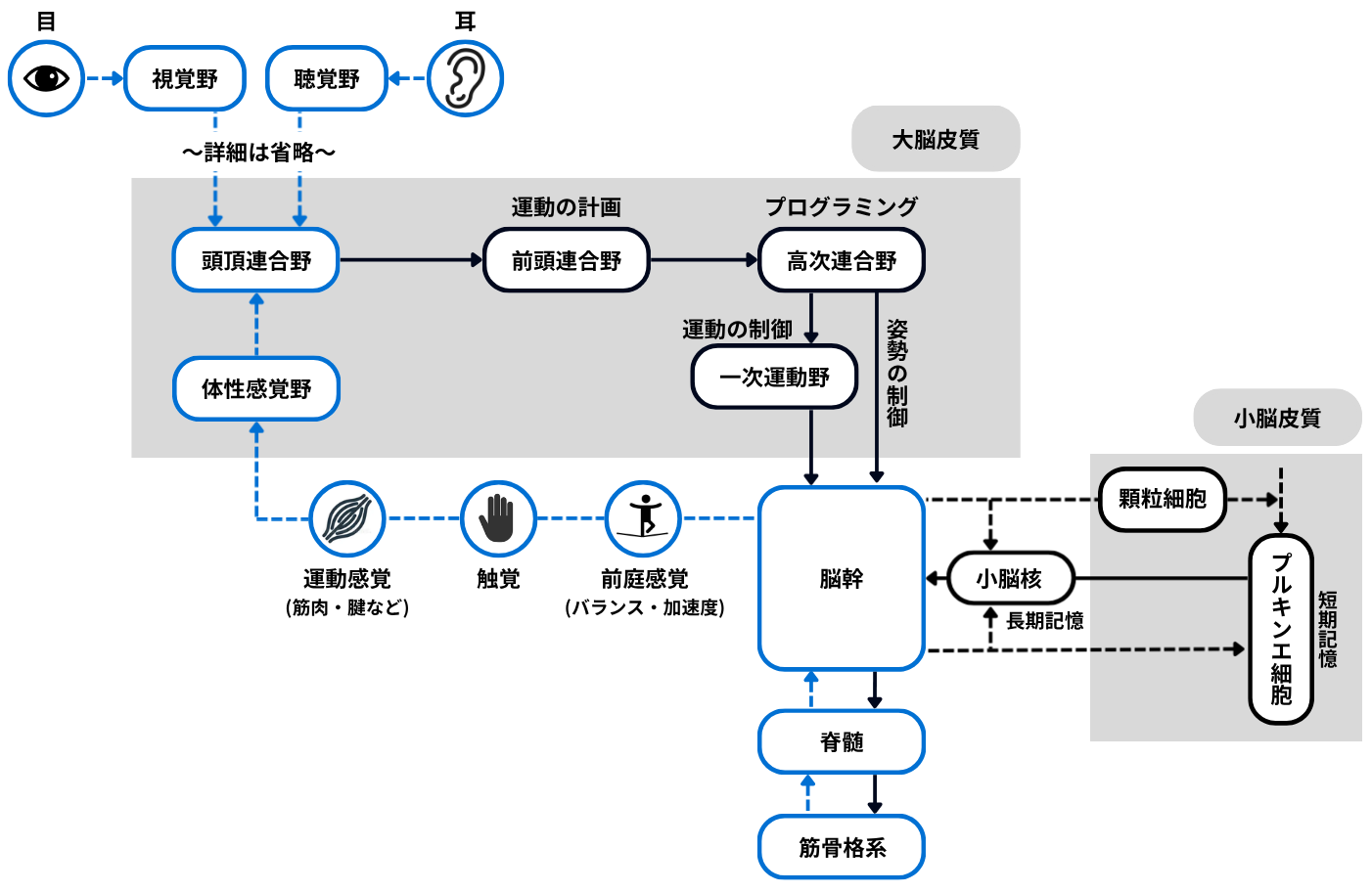
動作が開始された後も、スポーツ動作は続きます。
▶その時の状況に合わせて「次はどの様に動くか?」
▶必ずしも自分が思い描いているように動けない場合もあり、「想定外の状況ではどの様に動かすのか?」
これらの課題を解決するためには、「自分の身体が今現在どんな状況なのか?」
体性感覚 (バランス感覚・筋肉や腱・触覚)からこの情報を受け取り、再度プログラムをしていく必要があります。
「知覚→運動計画→運動指令→フィードバック→知覚へ戻る」という
この一連の流れを「フィードバック制御」と言います。
しかし、この体性感覚によるフィードバックは時間がかかると言われています。
具体的にどのくらい時間を要するかと言うと、
▶体性感覚 (バランス感覚・筋肉や腱・触覚) からフィードバックを受け取るのに「約0.03秒~0.05秒」
▶視覚情報からフィードバックを受け取るのに「約0.1秒」
▶聴覚情報からフィードバックを受け取るのに「約0.15秒~0.3秒」
この情報を受け取ってから、新たに動作をプログラミングするので、厳密にはさらに時間がかかると言われています。
近年のスポーツは、どんどん高速化しています。
水泳はタイムがあるので、分かりやすいですが、2025年のインカレ水泳でも、100m自由形の決勝ラインが「49秒台」辺りに上がってきました。
そんな状況下で、細かく考えて泳ぐ事は出来ないですよね。
そう、このフィードバック制御だけでは限界があるのです。
細かく考えていたら、サークルに間に合わないですし、力みます。
スピードも出せないので、レースなどには適しません。
これが、スイム練習は「基本考えない」と言う理由です。
ただし、「新しい動きを覚える時」「動きを修正したい時」これらの際には、適していると言えます。
▶ドライやウエイトの第一・第二段階は「考える」
▶︎ドライやウエイトの第三段階や水中のドリル練習、フォーム修正などのメニューは「初期は考える→反復して徐々に考えない様にして行く」
この様に考えている意図はここにあります。
水泳選手がより効率よくトレーニングをするために今回はここまで
とは言え、長く泳ぎ続けたり、スピードを上げても自分の身体を少しでも正確に動かし、理想の泳ぎを保ち続けないといけませんよね?
その為には、「初期は考える→反復して徐々に考えない様にして行く」という作業が必要な訳です。
実際にどうすればいいのか?
どんなメカニズムで考えずにできる (自動化させる) 様にして行くのか?
この辺りをまとめていきたいと思います。
https://www.threads.com/@suisapo_official
NSCA JAPAN アスリートにおけるS&Cと運動制御系トレーニングの融合|牧野 講平
→ この記事を書く際に参考にした教材。
Transfer of Dry-Land Resistance Training Modalities to Swimming Performance|Jerzy Sadowski 1,*, Andrzej Mastalerz 2, Wilhelm Gromisz 1
→ 水泳パフォーマンスに対する陸上レジスタンストレーニング介入の効果に焦点を当てた文献。
Schmidt, R. A., & Lee, T. D. (2011). Motor Control and Learning: A Behavioral Emphasis (5th ed.). Human Kinetics.
→ フィードフォワード制御・フィードバック制御を含む、運動制御理論の基本文献。
Shadmehr, R., & Krakauer, J. W. (2008). A computational neuroanatomy for motor control. Experimental Brain Research, 185(3), 359–381.
→ 小脳による「誤差学習」および「フィードフォワード制御」モデルの代表的研究。
Kawato, M. (1999). Internal models for motor control and trajectory planning. Current Opinion in Neurobiology, 9(6), 718–727.
→ 小脳が「内的モデル」を構築し、反復練習によって予測精度を高めるメカニズムを提唱。
水泳選手向けトレーニング種目・理論紹介に関連する記事
水泳選手のための筋トレの設計|筋トレを水泳に活かす考え方①
目標のタイムを出すために、ひとつでも上のレベルの大会に出るために、筋トレを取り入れるチームも多いと思いますが、以下の様な疑問を持たれたことはありませんか??
筋トレが水泳になかなか繋がらない。
どの様に設計をすれば良いのか分からない。
そもそも、水泳選手に筋トレは必要なの?
この辺りは、選手自身も良く理解していないケースもありますし、我々指導者側も、セミナーや文献を読みますが、自分の現場でその設備は再現できないというケースが多く躓くこともあると思います。
そこで今回は、実際に僕が大学チームで筋トレをどんな位置付けにしていて、どの様にトレーニングの設計をしているのか?
この辺りを紹介していきます。
水泳選手に「ウエイトトレーニングは良くない」という巷の噂について
多くのトップスイマー積極的に取り組んでいます。
しかし、巷では未だに「ウエイトをすると泳ぎが崩れる・硬くなる」と言う意見もあります。
最近では、ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸投手のトレーニング方法も話題に上がりますし、「ウエイトトレーニングをしなくても結果は出せる」というコメントも再注目されています。
イチロー選手も「体を大きくするためのウエイトトレーニングはしない」と話しています。
果たしてどうなのでしょうか??
今回はそんなホットな話題について考察していきたいと思います。
水泳選手にも知って欲しい【トレーニングの原理・原則】
水泳選手に限らず、トレーニングを行う全ての方に共通する基本的な考え方です。
トレーニングの理論を知り、練習メニューを意図を汲み取る事ができれば、トレーニングの効果を飛躍的に引き出す事が期待できるのです。スイサポでは、皆さんが自立して練習に取り組める様にサポートしてまいります。何かお困りな事があればお気軽にご相談ください。